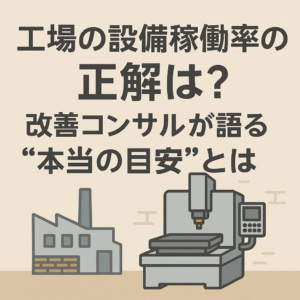工場のルールが形骸化する原因と、“人を信じる設計”への処方箋
こんにちは。工場改善サービスの田代です。
今日は「ルールを守らせる必要がなくなる仕組み」についてお話しします。
目次
■ ルールを守らせるのは、もう限界?
多くの工場では、
「ルールを守らせる」「注意を徹底させる」
というアプローチで現場を動かしています。
でも、正直しんどくありませんか?
・指差呼称してない!と毎日怒る
・手順書を見なさい!と毎日貼り直す
・あの人はいつも自己流で困る、とため息をつく
私は、思うんです。
ルールを守らないのは“怠けてる”からではなく、“守る理由が見えない”からだと。
■ お客様の顔が見えた瞬間、人は変わる
以前、あるお客様の工場でこんな改善を行いました。
それまでは分業体制で、各人が決められた工程だけをこなすスタイルでした。
でも、それだと「自分の作業がどんな製品になり、誰に届くのか」がまったく見えませんでした。
そこで、**一人の作業者が一製品を最初から最後まで仕上げる“多能工化”**に切り替えていただきました。
すると――
- 品質への意識がぐっと高まり、
- 製品の見た目まで丁寧に整えられるようになり、
- 最終的に「この製品、ちゃんとお届けできるかな」と、自発的に確認するようになったのです。
ルールを強化したわけではありません。
ただ、「自分の手で誰かに届ける」という実感を持てたことで、行動が自然と変わったのです。
■ 人は、迷惑をかけたくない生き物
これは私の信念ですが、
人は本来、“迷惑をかけたくない”と思って生きていると思います。
現場で手を抜く人だって、
→ 自分のミスで誰かが困ると「申し訳ないな」と感じている。
→ でも、誰が困るのかが見えないから、ピンとこないだけなんです。
■ 現場は「人と人の信頼」で動いている
ルールとは、本来「守らせるもの」ではなく、
**「信頼のリレー」をつなぐための“思いやりの約束”**です。
だからこそ、
- 次工程が誰かを明確にする
- 検査が誰のためかを伝える
- 出荷先がどのお客様かを共有する
といった仕組みをつくることで、
ルールは“人の顔”を通して自然と守られていくのです。
■ まとめ:ルールの先に、人がいる【資料プレゼント】
あなたの工場のルール。
その先に、誰の困り顔があるか?
誰の喜ぶ顔があるか?
見えるようにするだけで、現場は変わります。
人を信じる設計、始めてみませんか?
工程設計の考え方がわかる、資料をプレゼントしています。
お気軽に資料請求ください。